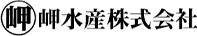「シラス」とは元々、鮎やウナギ、イワシ、ニシン、イカナゴなどの魚の稚魚の総称だ。 「シラスウナギ」という言葉もある通り、この種の稚魚は体に色素が少なく白色〜 透明色をしているのでこう呼ばれる。

そもそもこの「シラス」という言葉は、一説には時代劇でよく見かける白い砂利の敷かれた裁きの場所「お白州」からきているといわれ、シラスを干している様子、その一面真っ白な状態が、お白州に似ていたことから名づけられたともいわれる。いつしか、 色の薄い稚魚を総称してシラスと呼ぶようになった。(身体が白い子で「白子(しらす)」という説もある。)
江戸時代には、 主に地引網で獲られ、水揚げされていたが、 現代の様な冷蔵技術も迅速な輸送方法もない中で、足が早く傷みやすいしらすは、都市部にあまり流通することもなく、ほとんどは地元で消費されていた。何せ、現代の高級魚「マグロ」でさえ、その脂身の傷みの早さゆえにトロの部分は捨てられており、ほとんど雑魚のような扱いをされていた時代だ。都市部の人々にとっては、シラスといえばもっぱら、きちんと乾燥させたちりめんじゃこの様なものだったに違いない。
その後、明治大正と時代は移り、昭和から平成へと時を経るにつれ、漁獲法や冷蔵技術、そして流通も良くなり、加工技術もあがったことにより、現在の様に全国どこでも普通にスーパーでシラス干しが買えるようになったというわけだ。ちなみに、ただ茹でただけのものを「釜揚げしらす (釜揚げちりめん) 」、さらに天日干ししたものをしらす干しと呼び、 地方や乾燥の具合などによって、中干しシラス(太 白ちりめん・太白・やわ干し・やわ乾・しらす・しらす干し・普通干し)、上干(上乾) チリメン(ちりめん・ちりめんじゃこ・かちり)などのように呼び名が変わる。