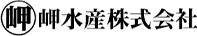お店の第一印象
日本の喫茶店や居酒屋で最も身近な「おもてなし」の象徴、それが布製のおしぼりです。布製のおしぼりは、日本では広く普及していますが、海外ではまだ一部の地域でしか見かけることがありません。しかし、外国の雑誌などでは「疲れを癒す白くて小さな名脇役」や「居酒屋で味わう隠し味」として紹介されており、少しずつですが確実に世界へと広がりを見せています。
日本の喫茶店や居酒屋に行くと、ほとんどのお店で布製のおしぼりが差し出されます。温かいおしぼりや冷たいおしぼり、直接手渡しするお店や、木製のおしぼり置きに置いてあるお店など、出し方には様々なスタイルがあります。しかし、共通しているのは、日本の「おもてなし」の心が込められている点です。おしぼりを差し出すこの習慣は、日本古来の伝統文化に根ざしています。
おしぼりの起源については、古事記にもそれらしき記述が見られますが、具体的なサービスの原型は室町時代に遡ると言われています(江戸時代との説もあります)。当時、旅籠屋では水桶と手ぬぐいを用意し、訪れた客の手足の汚れを拭い、旅の疲れを癒すことが始まりだったと言われています。室町時代といえば、柳生新影流の祖である柳生石舟斎などが活躍した時代です。石舟斎をはじめ、剣豪や歴史上の人物たちも、おしぼりに「ほっ」と一息ついていたのかもしれません。
おしぼりは、単なる清潔感の提供だけでなく、訪れる人々に対する心遣いと温かさを伝えるものであり、これこそが日本の「おもてなし」精神の一端を担っているのです。