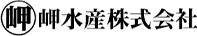南へ向かうカツオが脂を乗せて戻ってくる時期になりました。また、マイワシの刺身は、まるで大トロのような味わいです。北海道では、サケの漁が盛んになりサンマの漁獲も好調です。秋から冬にかけては、牡蠣の旨味が増し、冷え込む季節にはマダラやアンコウが出回り始めます。この時期は甘みを増した野菜と組み合わせる魚を使った鍋料理は格別です。
冬になると、深海の魚介も格別の美味しさを見せます。アカムツ(ノドグロ)やキンキは肉厚に太り、日本海を南下する10キログラムを超えるブリや、卵を持つハタハタは、冬の訪れと共に大量に捕れます。秋から冬にかけての魚介は、濃厚な「旨み」と「脂」で溢れていますね。

鮃(ヒラメ)
平目は字の通り平たい魚です。外国ではどのように呼ばれているのかというと、英語でも「flat fish」というそうです。平目は鯛と並んで白身の最高級魚。淡白でくせがなく、歯ごたえのある刺身の旨さは絶品!タンパク質を20%近くも含み、鯛と同様アミノ酸のバランスが良いからです。とりわけ縁側は人気があり食通の間にもてはやされます。
薩摩芋(さつまいも)
1600年ころ、中国→琉球→薩摩に伝わったので、サツマイモとよばれています。中国から来たいも=からいもともよばれていたそうです。今の埼玉県川越市あたりはサツマイモの産地で、江戸から二里あったので、ここから来る焼きいも屋のことを「十三里」とよんでいました。それにひっかけて、焼きいも屋が「栗(九里)より(四里)うまい十三里(9+4=13)」とふれて売っていたそうです。


栗
栗は、秋の味覚として、特に日本人に好まれている食材の一つです。ほんのりとした甘味と、ほくほくとした食感。イガに覆われた実がなっている様子は、秋の風物詩です。魚も果物も1年を通じて手に入るものが多くなっていますが、生の栗は、今でも限られた時期にしか手に入りません。栗は、縄文時代から近代に至るまで、大切な食料や用材として広く利用されてきました。日本人にとって、栗は切っても切れない深い歴史ある存在です。